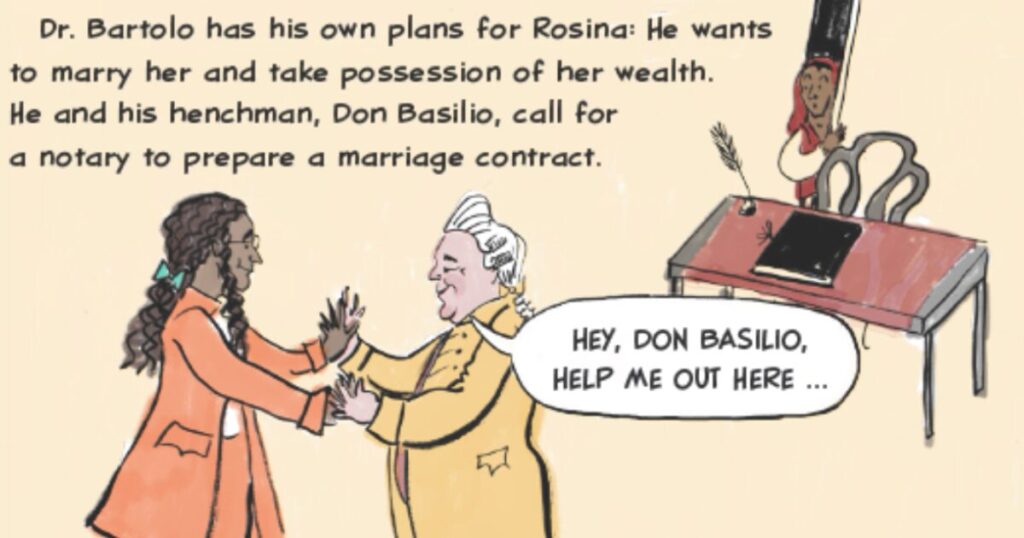公演詳細は
http://www.nntt.jac.go.jp/opera/jenufa/
在米時代の10年ちょっと前に、唐突にチェコのオペラを聴いてみたくなり、
たまたまCDショップにあった「イェヌーファ」のCDを入手、あの冒頭の「カタカタカタカタ・・・」に一気に引きこまれていっときハマった時期があり…チェコで制作された映画版とかも見たりしたこともあるんですが、実演は初めて。日本で観ると字幕の確認ができる…というメリットがありますが、その恩恵をしっかり受けてきました。
(ソフトリストも作ったことがあるのヨ↓)
http://www.geocities.jp/traeumereienvalencienne/soft-11.htm
名詞に性がある言語がいくつもありますけど、もし、オペラを性で分けるとすれば「イェヌーファ」は間違いなく女性性のオペラでしょうね。終始一貫、女性が主導権を握り、男たちは物語を膨らませるためのふくらし粉のような存在でしかないですから。
そんな男たちーイェヌーファの周りにいるラツァとシュテヴァ、なんでヤナーチェクは二人ともテノールにしたんだろうなあ・・と思います。余談ですけど、ヤナーチェクの「グラゴル・ミサ」もすごく素敵な作品ですが、テノールとバスの比率のバランスが著しく悪くて^^;バスはほんと、ちょこっとだけで物足りないんですが、テノールにはすっばらしく美しい旋律がつけられているんです。ヤナーチェク、テノールが好きだったのかしら^^;
一幕では、ほんと二人とも「ちょっと”足りない”んじゃないの・・」というくらい、頼りない。シュテヴァは一貫してダメ男ですが、イェヌーファの過去もひっくるめて愛する決意をし「いい人よねっ」なラツァにしても、勢い余ってイェヌーファの頬を傷つけてしまった前科があるんですし、いつDV男になるかわかんないよ・・という危険性を孕んでいるよな・・とも思います。
字幕を見ながら鑑賞していると、活発で明るい利発なイェヌーファも意外と軽薄というか、妊娠を盾にシュテヴァに結婚を迫るあたり・・・頬に傷をつけられる前に、既にシュテヴァはイェヌーファに飽きてるを無意識のうちに感じ取っていて
(もちろん閉鎖社会故の「恥の文化」が根底にあるんだろうけど)必死で繋ぎとめようとしているのが浅はかでもあり痛々しくもあり・・
「お前は利口だね」とおばあさまから言われても「私の知識なんて水の中に落ちちゃった」と言いながらお腹をそっと手で抑えた仕草は、女性としての本質を突いていると思いました。男に溺れてしまえば、女ってそういうものなんだと。
でも、そんな疵のある(頬の傷という意味ではなくって)イェヌーファだからこそ、目が離せないヒロインになり得るのでしょう。
コステルニチカがシュテヴァのことを「自分の血を分けた子供なのに見ようともしない」と罵ってましたが、血を分けた子供ではないイェヌーファを慈しみ、持てる限りの愛情を注いでいた彼女にとっては、あれこそ彼女がシュテヴァを許せなかった核心かもな・・と思いました。そんなことも、字幕を見ながら確認できたことの一つです。
イェヌーファが出産した後、薬を飲ませて眠らせるまでの二人のやりとりの旋律は、R.シュトラウスの「アラベラ」姉妹の女声2重唱にも通じる美しさだなあ・・と、あの場面は涙腺を刺激しました。あそこを聴いちゃったら、子殺しが発覚し、しょっぴかれる場面で「私はお前よりも自分のことだけ愛していたの」と言うのは本心ではないでしょ・・って、またウルウルしちゃいますよね。
演奏そのものは、必ずしも私のドンピシャ・・というわけではなかったし
(もちっとアクセント強めで、縦の線がパキっとしてるほうが好み)
歌手陣も、もちっとドラマティックな方がホントは好みなんですけど
(うちにあるコステルニチカって、元・ブリュンヒルデの往年のワーグナーソプラノ様ばかりなので^^;そーいう歌唱に慣れていると、ラーモア(←私にとってはうちにCDのある「ヘンゼルとグレーテル」のヘンゼル)の線の細さは若干物足りなかったんですが、力で押すだけがこの役じゃないんだな・・ということを納得させてくれましたし、コステルニチカって自分の中のイメージでは、50代中盤ぐらい?と思ってたんですが、よくよく考えてみたらもう少し若いのかも・・とも思いました)
ところどころに、私達日本人が聴くと、なんとなく懐かしいような、和風に感じる旋律も散りばめられてますし、演出も変な謎解きがなく、違和感がありませんでしたし、
なんといっても、作品の力・・でしょう。今回の上演が好評だったのはうなずけます。
そして、私の往年のアイドルでもある(シェローリングファンならきっと誰しも・笑)ハンナ・シュヴァルツ様✨御年73歳にはとても見えません!
確かにもう「おばあさま」なんですが、なんと美しい、そして舞台さばきの素晴らしいこと!(双眼鏡で何度もガン見してしまったわ〜〜)
今回、急遽「サロメ」のヘロディアスも歌うことになったということで、若干声はお疲れ気味だったかもしれませんが、それでも大方のご意見同様、声が一番飛んできましたし、3幕でコステルニチカが子殺しが発覚する前に「私を支えて下さい!」と彼女にしがみつくところの「どうしたんだい?」というあの低声にはゾクッとしました。