【近大司書通信】情報資源組織論レポート合格体験記と試験対策|司書資格取得者が語る学習法
近畿大学通信教育部の情報資源組織論レポート体験記と、科目終末試験の対策についてご紹介します。
*レポート&科目終末試験の解答、語句の解説は掲載していません。
レポート作成前に見たい動画
情報資源組織論担当のA先生が解説して下さっている以下の動画を見てから取り組むと、学習の概要が掴めます。
レポートについて
レポート提出から合格まで
- 10/1提出 → 10/11 不合格 返却日数:11日
- 2/17再提出 → 3/5 合格 返却日数:16日
レポート設題大意(2025-26年度も変更なし)
「指定したキーワードをすべて使って、各設問の解答を完成させてください。」
- 集中目録作業と分担目録作業(=共同目録作業)、それぞれの特徴を明確にし、さらに今後の目録作成業務のあり方について自らの見解をまとめてください。(1,000字)
<キーワード:MARC、集中目録作業、分担目録作業、総合目録、書誌ユーティリティ> - 地域の図書館(公共図書館)の「蔵書の所在記号(背ラベル)の付与のしかた」について複数ケースを洗い出し、気づいたことをまとめ、さらに調査で得た内容や関連情報をもとに、書架分類と書誌分類という二つの点から、NDCの分類(記号)を活用することの意義や課題について考察してください。
<キーワード:書架分類、書誌分類、目録、配架(テキストでは排架を使用)、所在記号>
む、難しい…
学習初期に4科目提出した科目の一つ。レポート執筆順は2番目でした。3連続再提出のうちの1科目です。
この科目は「情報サービス論」同様、演習科目(スクーリングorオンデマンド)受講の為に必須なので、学習初期の段階で提出する方が多いと思われますが、難しいです。
まず教科書が近大が作成したものではなく、樹村房社出版の「情報資源組織論」なのですが、これを読み込むのは非常に難しい。図書館専門用語もさることながら「図書館情報技術論」同様、コンピュータ関連用語がたくさん出てきます。
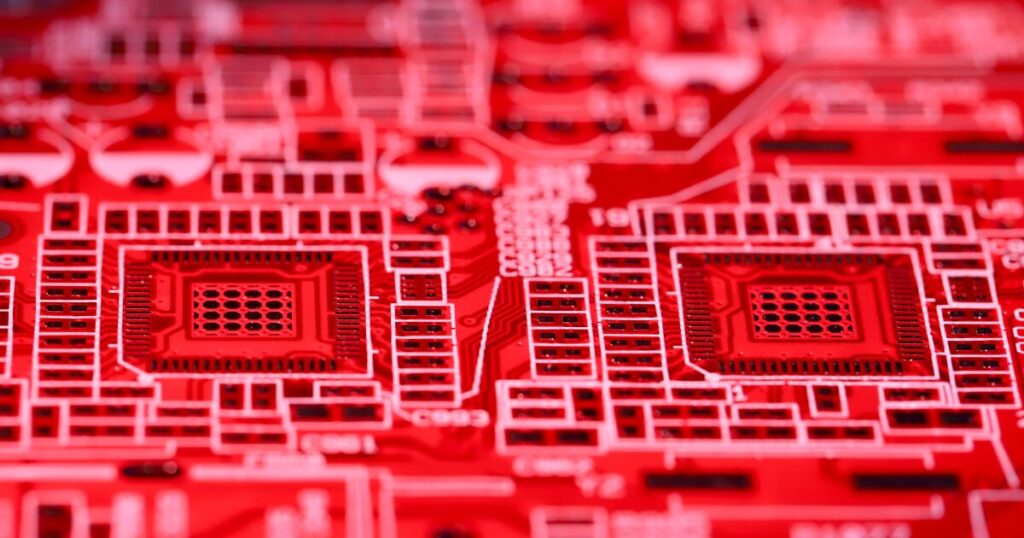
また、全科目受講修了した今だから言えますが、
他の科目との結びつけがしにくい。同じくIT系の「図書館情報技術論」は資料のデジタル化などに関しては「図書館情報資源特論」などと結びつけ、相互での応用が可能ですが、
この科目に関しては、これ単独で掘り下げ、学んでいかねばならない。
と思います。レポートを書き始めたのは2科目目で、そもそも他の科目の知識がほぼ皆無状態だったので意識していませんでしたが、レポート再提出と試験の再受験を終盤に持ってきたことにより、そのことに気がつきました。
そういう意味でこの科目だけは、特別かもしれません。
語句の理解のために用いたのは「図書館情報学用語辞典 第5版」です。
(ジャパンナレッジにも搭載されています。)

レポート作成の注意点
レポート設題は上記のように、2つに分かれています。
語句の意味をしっかり捉えていることが重要になります。
私は設題1に関しては一度目で「概ね要点を押さえてまとめられていると思います」との講評、2に関しては、字数を稼ごうと考えた結果、調査対象館での背ラベルの解説に大半を費やしてしまいました。再提出となった時の講評を紹介します。
設題で求められているのは書架分類と書誌分類という二つの点からNDCの分類記号を活用する意義や課題について考察することですので、まずはそれぞれの分類でNDCがどのように使用されているかを考えてみましょう。
現在の図書館では、書架分類は排架場所を決めるための所在記号として、書誌分類はOPACで主題検索を行うために用いられていますが、それぞれにNDCを使用すると具体的にどのようなメリットがあるのか、反対にNDCではカバーしきれない点は何かなど、NDCが備えている様々な特徴を踏まえて意義や課題について考えてみてください
実は書架分類と書誌分類の違いが書籍だけではなかなか飲み込めませんでした。
そのため、レポート再提出も暫くほったらかし。2月に本校対面スクーリングで「情報資源組織演習」の授業1回目を受け、やっと自分の中でなんとなく「腑に落ちた」ので、ようやくレポートの再提出に踏み切ることができました。
再提出の際は、設題1に関しては前回書いたものをそのままタイプしましたが、問題ありませんでした。(一つ合格していても両方書かねばならないKULeDの仕組み…)
参考文献の書き方は【近大司書通信】レポートの参考文献記入が劇的に楽になる!国立国会図書館サーチの活用を参考にしてください。
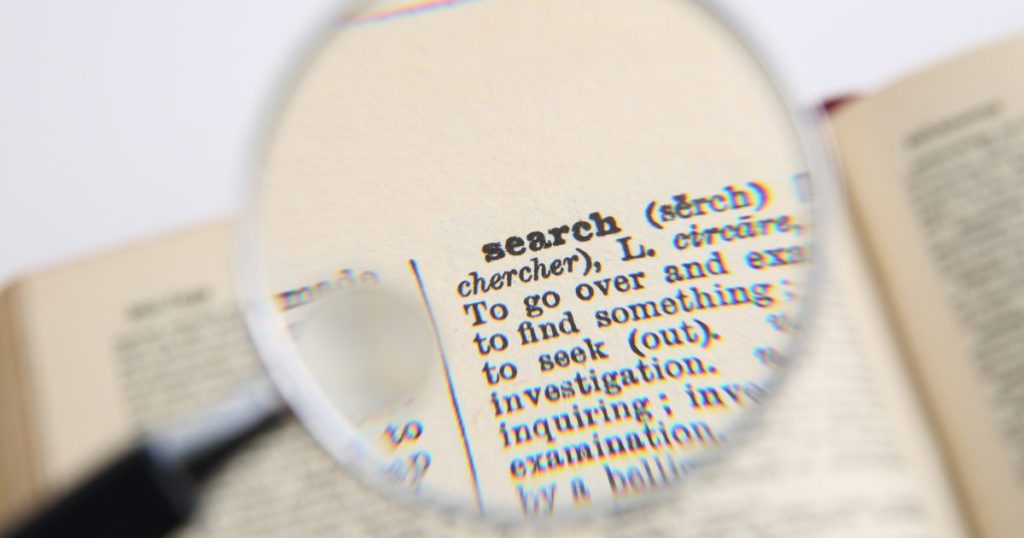
科目終末試験について
受験のタイミング
試験対策としても「情報資源組織演習を受けた後の方が理解しやすかった」と仰る方が多いので、演習を受けはじめてからの受験をお勧めします。
オンデマンド、対面スクーリング共に申し込み期間が予め決められています。要項をしっかり読んで、ご自身が希望する演習の申し込み忘れのないようにしましょう。
試験結果
- 2024年12月1日 受験 → 2025年1月9日 不合格(不可・50点)
- 2025年3月9日 再受験 → 2025年4月22日 合格(良・70点)
出題
どちらも「教科書等の内容をそのまま抜き出すのではなく、自分の言葉で記述して下さい」との注意書きもありました。
1回目
「目録に求められる基本機能のうち、資料の識別・選択・入手に該当する『日本目録規則2018年版』における「目録の機能」について述べなさい」
2回目
「典拠コントロールについて、典拠ファイルあるいは典拠データを作成する理由について述べなさい」
不合格となった1回目はおそらく字数は500文字程度だったと思います(行数にして18行)
だって語句の理解が全然できてなかったし…
まとめ
この「情報資源組織論」と先日紹介した「図書館情報技術論」の2科目は、レポート、試験共々に難易度が高かったと仰っている修了生の方々が多いです。私もそう思います。
難易度を高めている理由は
- 「情報資源組織論」の提出はオンデマンド/対面スクーリング授業の「情報資源組織演習」の受講申し込みに必要なため、まだ図書館学への理解が浅い受講初期の段階で早めに出す方が多い
- 司書を目指す方は(自分もそうなんですが^^;)「ザ・文系脳」の方が多いとおもわれる為、理系寄りのIT系、情報系に係る両科目の技術の話は受け付けにくいのではないか?
- 他の科目との結びつけがしにくい。同じくIT系の「図書館情報技術論」はデジタル化など資料の保存に関しては「図書館情報資源組織論」などと結びつけ、相互で応用が可能ですが、この科目に関しては、これ単独で掘り下げ、学んでいかねばならない。
などかと察します。対面スクーリングを受講予定の方は、直接先生にわからないことを聞いてみるのも有効です。
ここを乗り越えたら資格取得への道がググッと近づきますので、地道に頑張ってくださいね💪
この記事が、皆様のレポート作成と科目終末試験のお役に立てれば幸いです。


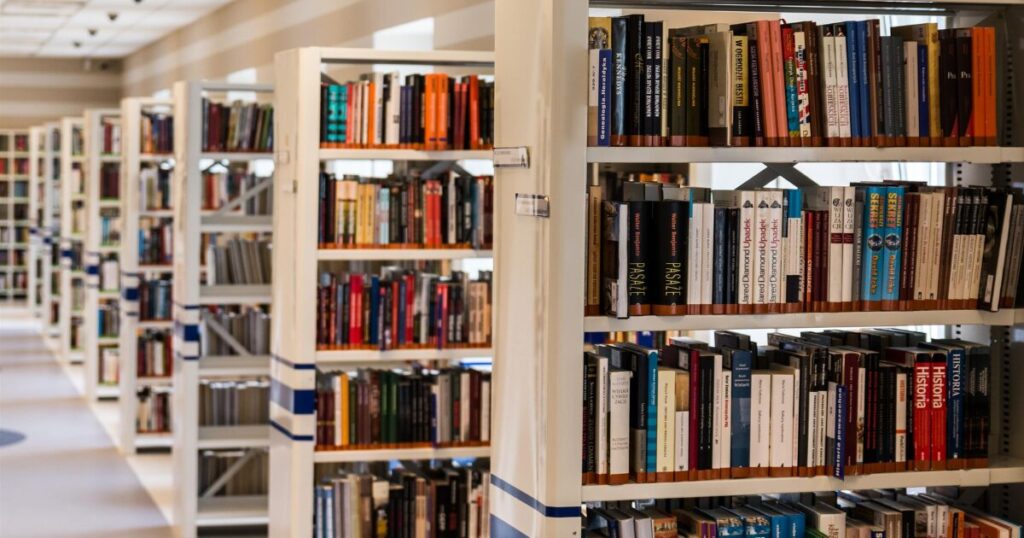

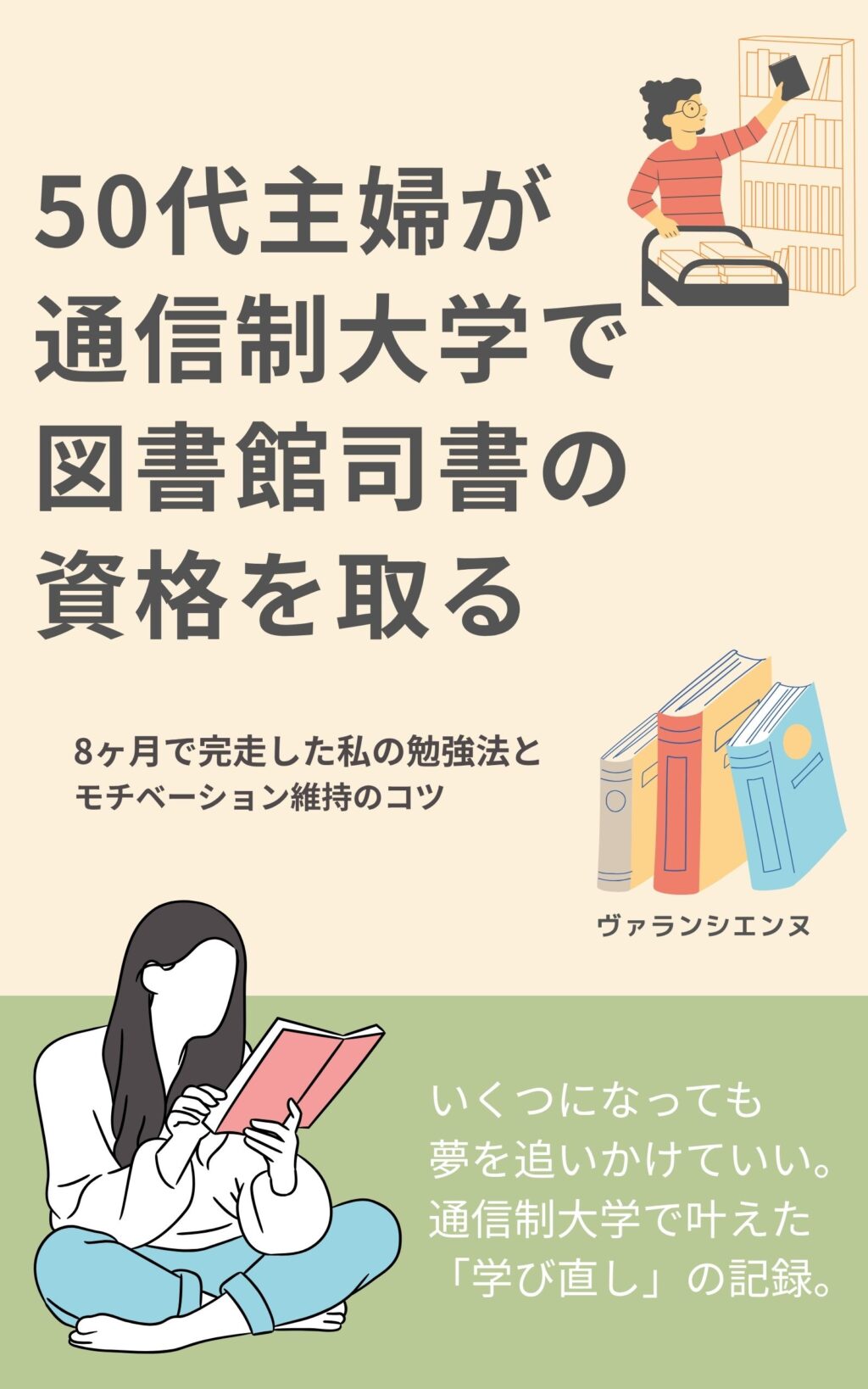
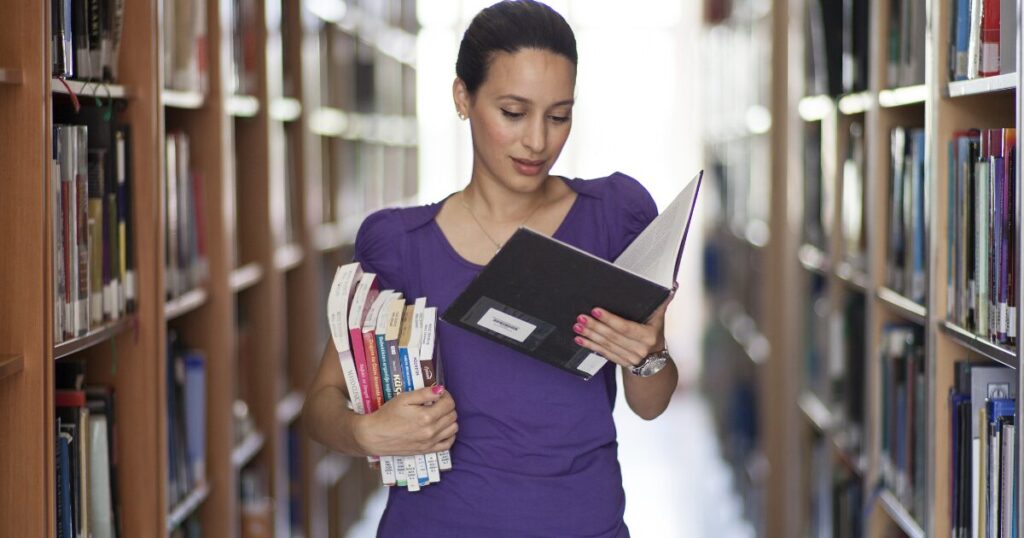

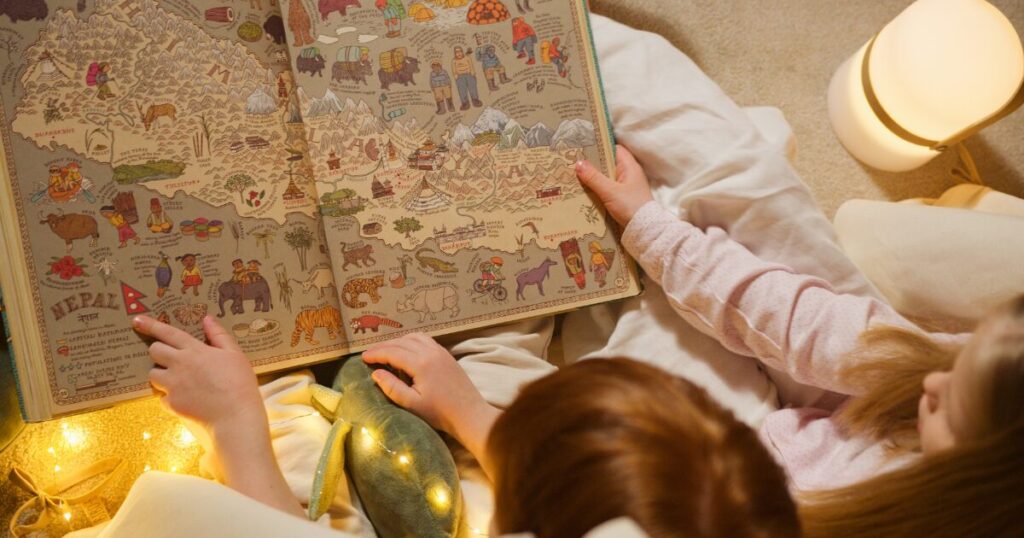


コメント