これは私のご贔屓さん、アレクサンドル・ヴィノグラードフが2015年、ブエノスアイレスのコロン劇場で初めてフィリッポを歌った時に、Webradioで聴いた蔵出し感想です。
オペラ「ドン・カルロ」について
史実、またシラーの戯曲での扱いはともかく、オペラとしての「ドン・カルロ」は主要登場人物それぞれに魅力があり、それぞれが黒い部分も合わせ持っている・・どちらかというとドイツオペラ寄りの嗜好の方でも、この作品だけは別・・とおっしゃる方も多いのは、その多面性とバランスの良さに依るものかもしれません。「一人にフォーカスするのではなく、全体を俯瞰する楽しみ」が味わえる・・そんな作品だと思っています。
フィリッポという人物
と言っておきながら、これから長々とフィリッポのことを語るのもなんなのですが、かつて某オペラの解説書に「この作品は【ドン・カルロ】ではなく【フィリッポの憂鬱】とかにするべき・・云々とかいう文言を見たことがあって、え〜〜そりゃ違うでしょ!と(バス歌手のファンのくせに^^;)思っている私。
だって、フィリッポって矛盾は多いし突っ込みどころ満載じゃないですか。
- 息子は言うこときかないし
- 嫁からも愛されてないし
- 大審問官には頭が上がらないし
- 国内情勢不安定、政治的にも危うい状況 ← 異端審問の場面を見るにつけ「あんまり民衆から支持されてないよね・・」と思うわけ
出てきた時から嫁をいじめるし、政治的な匂いをプンプンさせてるし、異端審問の場面では、自分のために剣を抜いてくれたのはロドリーゴただ一人だけだし、で、あの場面、火あぶりだのなんだの・・
からの〜生々しい場面の後、いきなり(幕が変わって休憩を挟むとはいえ)「Ella giammai..(彼女は私を愛していない・・」とか急に歌い出すし^^;
その後も大審問官に罵倒されるし、エリザベッタからも反抗されるし(んで逆ギレするし^^;)この後はまた、為政者としての立場での登場で・・あのアリアだけがちょっと異質・・というか、あれがある故に複雑な役・・になるのでしょうね。
あれがなければ「ルイザ・ミラー」のヴァルター伯爵(父子対立という点ではフィリッポ父子に通じるところもあるけど、大義名分に拘って徹頭徹尾冷徹だし)やじーさん(笑)のくせに、若い人たちと張り合って権力に任せて女性に執着する(でも負けるw)「エルナーニ」のシルヴァと同じぐらいの役回り(平たく言えばただの嫌なオヤジ^^;)に成り下がる気がします。
しかーし!あのアリア(フィリッポの本音・・というか、弱さ、心情吐露)がある故の複雑な役・・ということを、すんなり納得させてくれるフィリッポがなかなかいないのが実情で・・
つまり、あのアリアを仰々しく「俺の素晴らしいバス声を聴けw」と、ただ感情に任せて歌うだけでは、フィリッポの多面的で矛盾を孕んだ性格は反映されないと思うんです。(また、旋律が美しいからつい歌っちゃうんだろうな〜〜とも思う。。。)

アレクサンドル・ヴィノグラードフのフィリッポ
で、私がヴィノグラードフのフィリッポを聴いてビックリしたのは
- ヴァルター伯爵やシルヴァを歌った時のような、観るひとにたいしてある種のこっ恥ずかしさ(悪人に見せようと頑張ってるけど、若さと人柄の良さが否めないね・・的な)を与えなかった!
(映像見たら考えが変わるかも・笑) - 最高音(大審問官とのやりとりの後のアレ)から低音まで、ほぼムラなく、無理なく鳴らしてる!もともと音域は広い(だからバリトンでも高音がきっついひとがいる第九のバスパートも無理なく歌っちゃう)と思ってたけど、これで確信した
- 言葉の間合い(無音の「間」みたいなもの)の取り方が絶妙
(ロドリーゴに言う”Non Sembre!”とか、あんなにはっきり聴こえたのは初めて・・←いままでまともに聴いてなかったとも言えよう) - 全体を通して聴くと、厳しさや激しさの方が勝ってるし、これならまだ肉体的にも枯れてないフィリッポだね・・
(覇気りんりんって感じじゃないんだけど、エリザベッタと閨を共にできないことからエボリにちょっかい出して、エボリが誘惑に逆らえなかったと言い訳するんだから、男盛りな男としての魅力を感じさせた方が面白い・・というか、それこそヴァルター伯爵とかシルヴァみたいになっちゃったらちょっとね〜〜みたいな^^;) - なんだけど!アリアでは一転、しっとり、しみじみ・・から始まって、後半にピークを持っていく感じで。
まとめ
そう!そーなの!こうやって歌ってくれると、腑に落ちるのよ、キャラクターとしてのフィリッポの矛盾点とか、心の痛みとかね。激しいだけじゃダメ、仰々しく大上段に構えてもダメ、ずーっと怒ってるだけみたいでもダメ、こういう色合いつけてくれないと。品格もあるし。
それで号泣してしまった・・んですけど、ね。

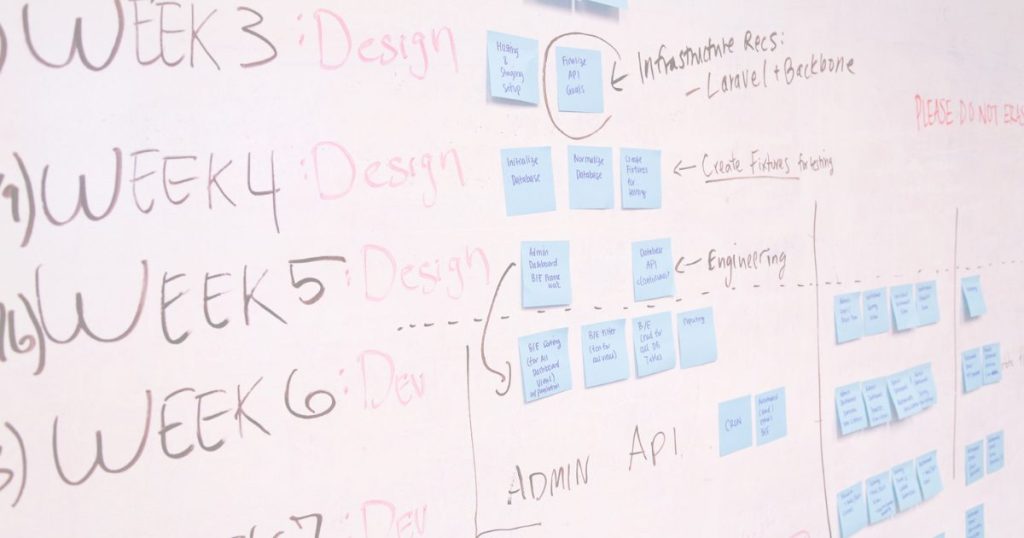









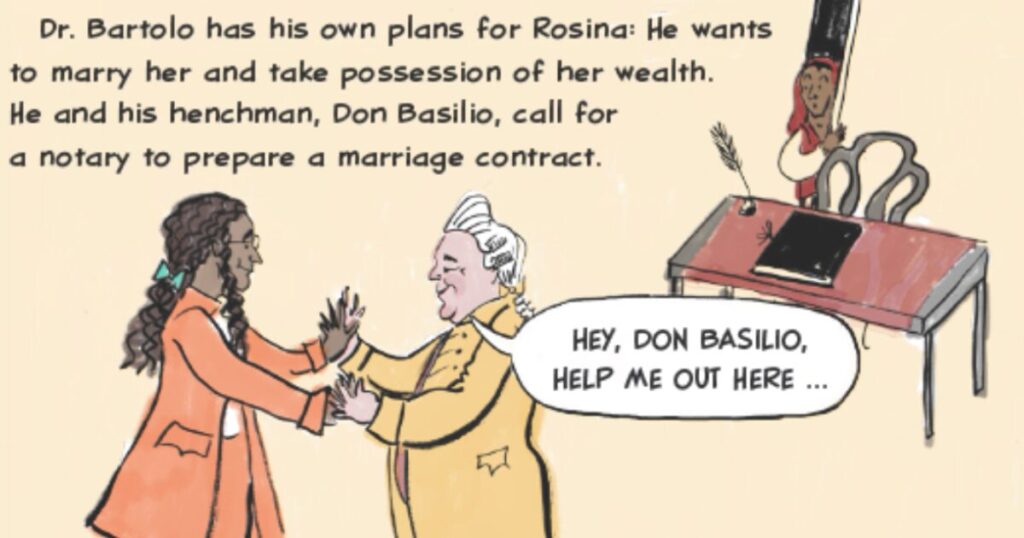
コメント