👇発売中です!
2024年10月から近畿大学通信教育部 科目等履修生として、司書資格取得コースで勉強をしています。現在、3月9日に再受験した「情報資源組織論」の試験結果待ちですが、他の科目はすでに単位を取得済みです。
レポート提出順番と返却日数(再提出含む)
今回は改めて私のレポート提出順番と、提出後の返却日数をまとめておきます。
- (再)は再提出を意味します。
- 一発合格 – 6科目
- 再提出後、2回目で合格 – 5科目
実際のレポート提出順(単位をとった順番ではありません)
- 情報サービス論 10/1提出 → 10/7返却(再) → 10/18再提出 → 10/31合格
返却日数:1回目 – 7日、2回目 – 13日 - 情報資源組織論 10/1提出 → 10/14返却(再) → 2/17再提出 → 3/5合格
返却日数:1回目 – 11日、2回目 – 16日 - 図書館情報技術論 10/1提出 → 10/27返却(再) → 12/27再提出 → 1/24合格
返却日数:1回目 – 27日、2回目 – 28日 - 図書館情報資源概論 10/1提出 → 11/25合格
返却日数:56日 - 図書館情報資源特論 10/15提出 → 12/20合格
返却日数:66日 - 図書・図書館史 11/19提出 → 12/14合格
返却日数:25日 - 児童サービス論 12/9提出 → 12/30返却(再) → 1/31再提出 → 2/20合格
返却日数:1回目 – 21日、2回目 – 21日 - 生涯学習概論 12/10提出 → 12/30返却(再) → 2/28再提出 → 3/19合格
返却日数:1回目 – 20日、2回目 – 19日 - 図書館制度・経営論 1/14提出 → 1/28合格
返却日数:14日 - 図書館概論 1/24提出 → 2/14合格
返却日数:25日 - 図書館サービス概論 1/28提出 → 2/14合格
返却日数:17日
最初の3科目は3連続再提出…
ご覧のように最初の3科目は連続再提出でした……。
10/18に情報サービス論を再提出後 → 11月上旬に情報サービス演習(スクーリング) → 11/10に初めての科目終末試験… が重なり、レポート作成は1ヶ月以上止まってしまいました。
学習初期に考えていた提出予定
- 情報サービス論
- 情報資源組織論
- 図書館情報技術論
- 図書館情報資源概論
- 図書館情報資源特論
- 図書館概論
- 図書館サービス概論
- 図書・図書館史
- 児童サービス論
- 生涯学習概論
- 図書館制度・経営論
当初の予定では、図書館概論とサービス概論は図書館情報資源特論と図書館史の間にやるつもりでしたが、準備に時間がかかると思われた為、息抜きに得意の歴史系に着手。12/1の試験締め切りギリギリの11/19に提出しました。
Googleスプレッドシートで作った進捗状況管理シート

Googleスプレッドシートで作った進捗状況管理シート
↑のような進捗状況表をGoogleスプレッドシートで作って、スケジュール管理をしていました。これと合わせて「受験計画表」が役立ちました。
🔗受験計画表の活用🔗
図書館概論とサービス概論は〇〇のチェック必須?!
図書館概論と図書館サービス概論はインタビュー必須だと思い込んでいましたが、実際に必須なのは概論のみ。そして図書館へ出向く必要はなく、私はメールで済ませました。これは2025年1月18日に行われたY先生の講演会で、先生も推奨なさっていました。
図書館概論は学習初期 or 終盤???
図書館概論は、近大も推奨しているように学習初期にやった方がいいと言われていますが、そうとも言い切れません。私の周辺でも、初期と終盤にやった方々が半々くらいですが、私自身は終盤に持ってきて正解だったと思っています。
いわゆる「図書館とはなんぞや?」という科目ですし、他の科目をこなしているうちに、繋がりが体感できるようになり、学習の理解が深まるとともに、レポートへも反映できたと感じました。
後回しにしていたお陰でY先生の講演会の後に着手出来たこともラッキーでしたし、講評でも、とても褒めて頂けました。
学習における、私のメンタルズダボロ時期
2回、どうしようもない時期がありました^^;
1回目は10/1に出した4科目中3科目が軒並み再提出になった時。同期のお仲間様たちが次々と「初めてのレポート、合格しました!」というのを目にするのがキツかった。あまりの辛さに、しばらくSNS断ちを敢行したほどです。直後の11月上旬、スクーリングで気が紛れました。つまづいているのは自分だけじゃないと、リアルな声を聞いて救われた感じ。
2回目は、年末に生涯&児童の2科目が、かなり刺々しいメタクソの講評で再提出になった時。心の底から見るのも嫌になり、お正月にかこつけて学習自体ほっかむり^^;
とにかく、一通り全科目提出&試験受験したい気持ちを優先
学習初期から、とにかく一通り全てに手をつけておきたい気持ちはずっと持っていました。再提出5科目中、さっさと片付けたのは最初に戻ってきた「情報サービス論」だけ。他は後回しにして(情報資源組織論なんて、10/14に戻ってきたのに、再提出したのは2/17ですよ)気持ちを切り替えてから取り組みました。
お陰で試験も2月までに全科目受験することができました。幸い、これまで不合格だったのは12月に受験した情報資源組織論の1科目で、3月に再受験して、4/22の結果待ちです。
学籍は1年間ですので、学習ペースとしては早い方(勿論もっと早い方もいらっしゃる)だと思いますが、実はこの学習を通して、自分は目標が先すぎるとダレてしまう習性だということに気づき、先を急ぎました。
他の方の進捗状況は諸刃の刃だけども
他の方の進捗状況は、良くも悪くも使い方次第の諸刃の剣。最初の頃に、そのことで気持ちが揺らいだ私が、なぜこうして進捗状況やスケジュールを公開しているかというと
- 大まかな流れを決めておく
- 再提出になったら目先を変えてOK
- 最初のつまづきが多くても、こまめなスケジュール調整で挽回できる
ことをお伝えしたいからです。
競争でも選抜試験でもないよ
この学習は競争でも選抜試験でもなく、所定の単位を取得すれば誰しも修了できるものです。お仕事や育児と並行して頑張っていらっしゃるお仲間の方たちには、本当に頭の下がる思いです。皆様それぞれに、立ち止まったり走ったり歩いたりしながら、マイペースで頑張りましょ!!
ランキング参加してます🎵
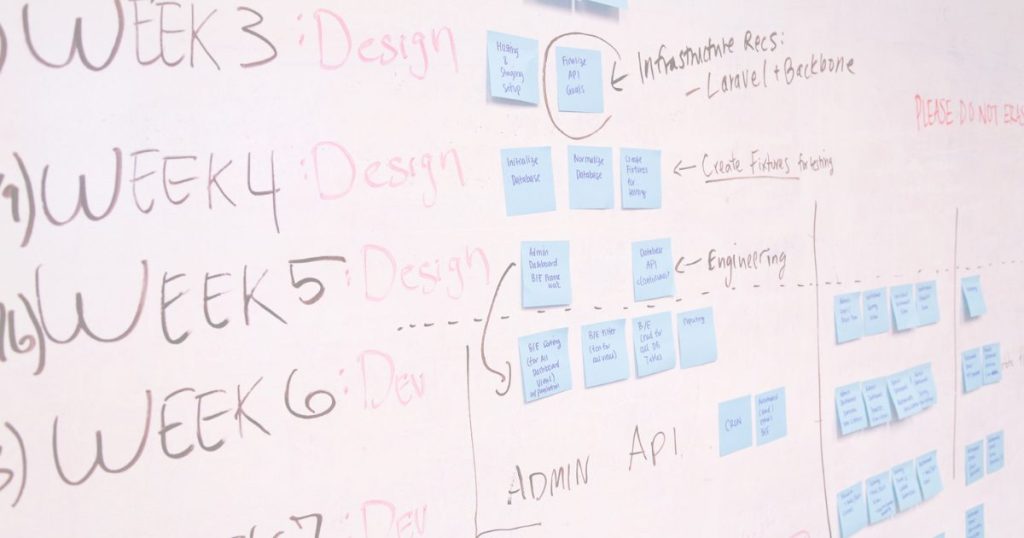



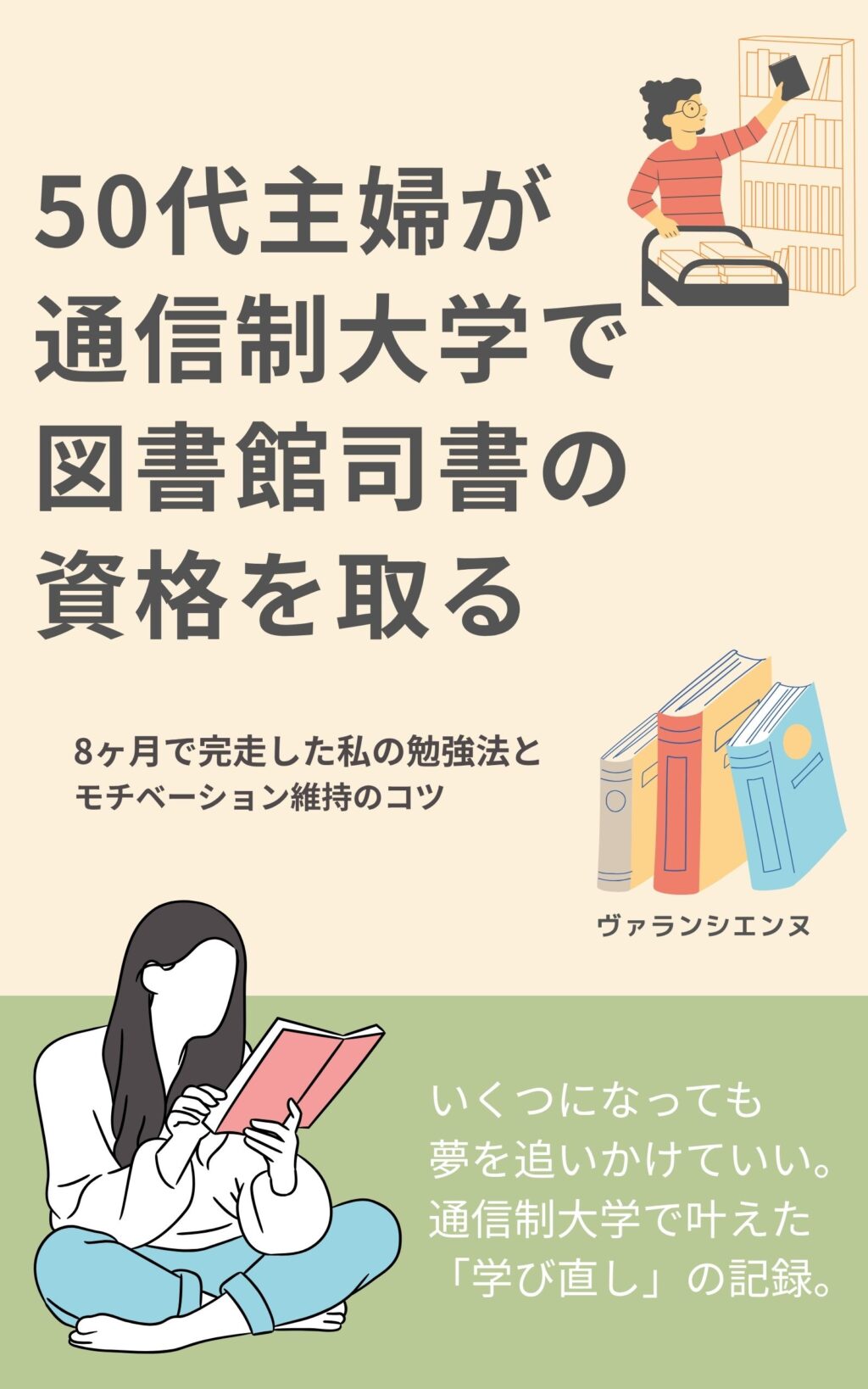
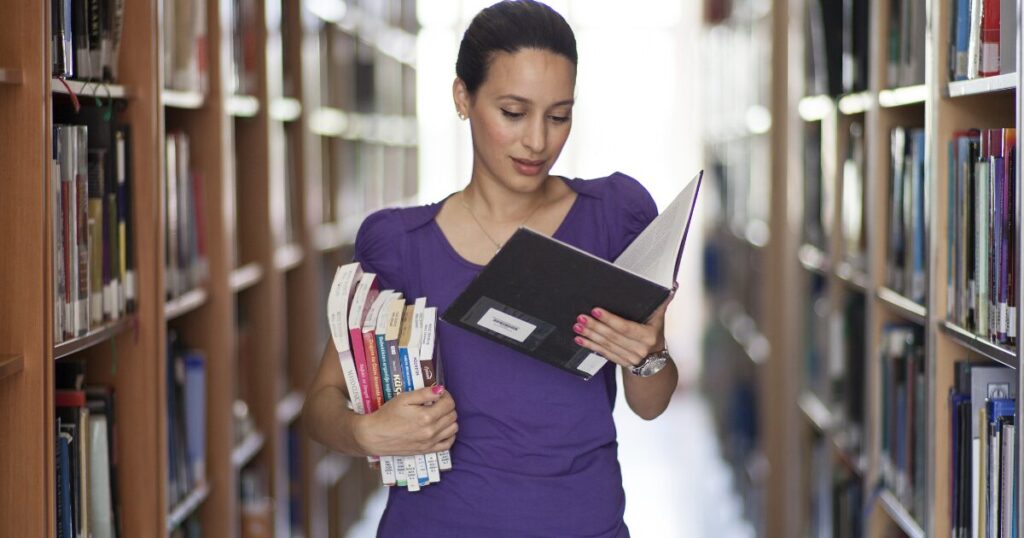

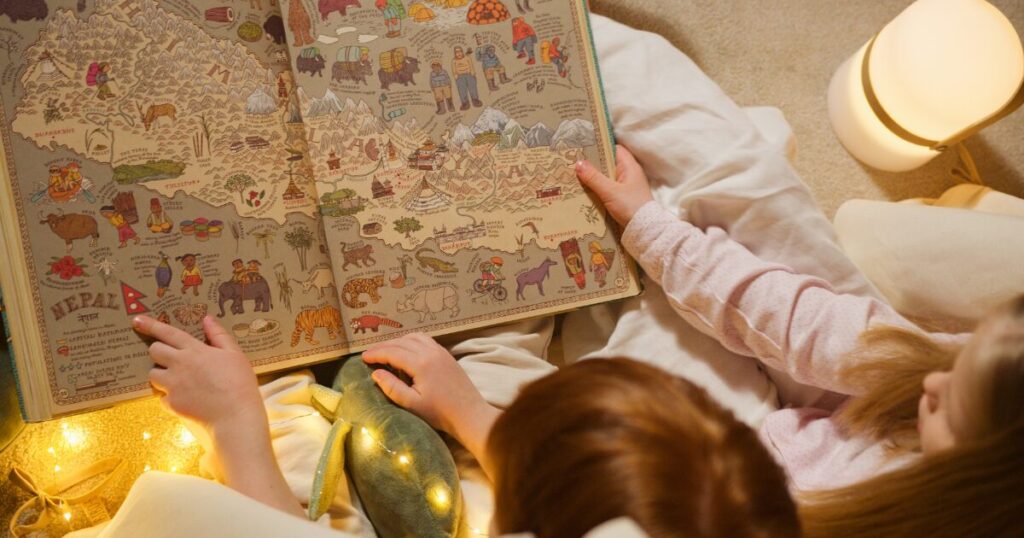

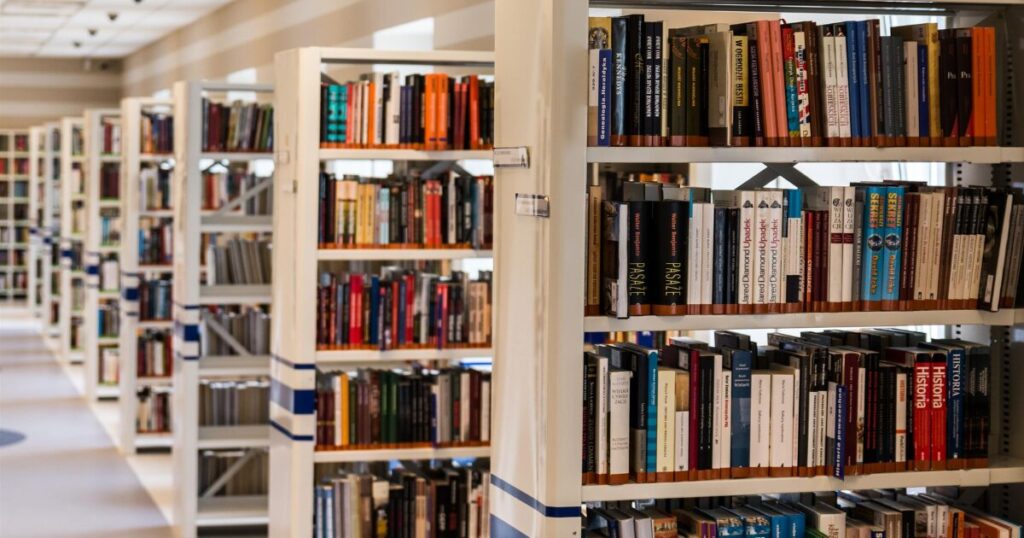

コメント