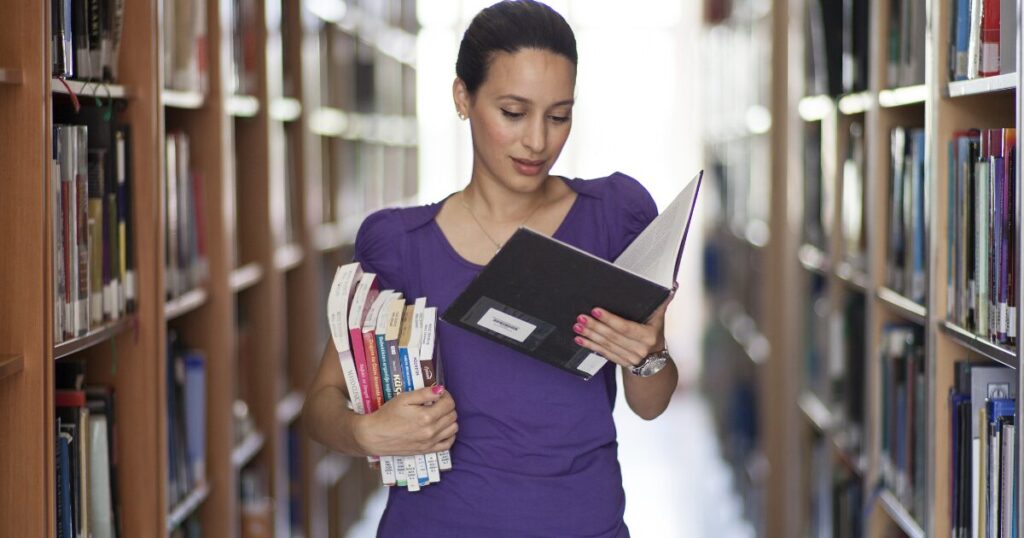元々全然社交的ではないので、時々人とお喋りするのが至極苦痛になる。
ネットでもその傾向があって、わいわい盛り上がっているところに自分が入って行くと水を差すようなことになるんじゃないかな?とか思うと、上手に入って行くことができない。
最近はそういうことがあまりなくなってきたと思っていたけど、ここのところ、またそういう病気が出ているようです・・・
こういう時には見ない、聞かない、言わない・・がお利口なのでしょう。
普段のときならいいけど、これが11月の彼の来日の時に当たってしまうと、4年前のようなことになっちゃうんだろうなーー;
それが一番怖い。
それにしても、ドンジョの演奏に様式美を求めるのは、もはや不可能なんだろうか…魅力のない声に過度に誇張された表現、歌はズルズルで崩しまくり。
これが現代のトレンドなんだろうか。だとすれば、もう時間とお金をかけてわざわざ飛行機に乗って聴きに行く価値も見いだせない…と思うのは、私の頭が固いせいだろうか?